龍谷大学の瀬田キャンパスに隣接し、38ヘクタールという広大な土地に広がる「龍谷の森」。学生向けのフィールドワーク実習の場として利用するとともに、地域住民と連携した取り組みも行ってきたことなどにより、生物多様性が保全されている点が評価され、2024年に関西の私立大学で初めて環境省の「自然共生サイト」に認定されました。「龍谷の森」の現在地、そしてめざすべき未来について、サステナビリティ推進室ディレクターの村井啓朗さんにお話を伺いました。

龍谷大学独自のネイチャーポジティブ宣言
————龍谷大学のサステナビリティ推進室の業務についてお聞かせください。
村井:大学としての脱炭素対策やネイチャーポジティブ、サーキュラーエコノミー(循環経済)に向けた取り組みを進めつつ、グリーン人材育成に関わる、さまざまな事業も実施しています。「龍谷の森」の方向性をまとめることも、重要な業務のひとつです。大学がこのような立派な森をキャンパスの間近に持っていることに魅力を感じますし、全国的に見ても素晴らしい事例だと思います。
————2024年3月に発出された「龍谷大学 ネイチャーポジティブ宣言」とは?
村井:ネイチャーポジティブとは、生物多様性の損失を止め、回復軌道にのせることを意味します。ネイチャーポジティブという考え方は民間企業含めて急速に注目度が高まっており、世界中で宣言が出されたり、具体的な取り組みや情報開示が進み始めている状況です。そのような中、龍谷大学は国内の大学として初めて、ネイチャーポジティブ宣言を出しました。
〈龍谷大学ネイチャーポジティブ宣言〉
①仏教の観点から、教育研究活動を通じてネイチャーポジティブに寄与する人間を育成します
②人文・社会科学から自然科学まで幅広い知見を有する大学として、ネイチャーポジティブにかかる研究成果を社会実装します
③国・地方自治体・企業・NGO・NPO等と連携し、ネイチャーポジティブに向けた諸活動を推進するとともに、新たな価値創造に向けた取り組みを共創します
④これらの活動に留まることなく、自身の行動を省み、自然と共生する世界の実現に向けて取り組みます
宣言では上記4項目が提示されていますが、前文にも龍谷大学の思いが込められていると感じます。具体的には、「仏教に『衆生』という言葉があります。『生きているもの』という意味です。『すべての生きているもの』という『一切衆生』という語を仏教はとりわけ尊重します。
古来、仏教は生きものの多様性に着眼していました」という文頭は、龍谷大学ならではの視点でしょう。自らを省みて他を利する「自省利他」の行動哲学を掲げ「仏教SDGs」を推進してきた龍谷大学が、ネイチャーポジティブ宣言を出したことは、これまでの流れの延長線上にあり、違和感がなく、かつ意義深いと私は考えております。龍谷大学だからこそやれること、やるべきことがあると思います。
環境省の「自然共生サイト」認定を受けて
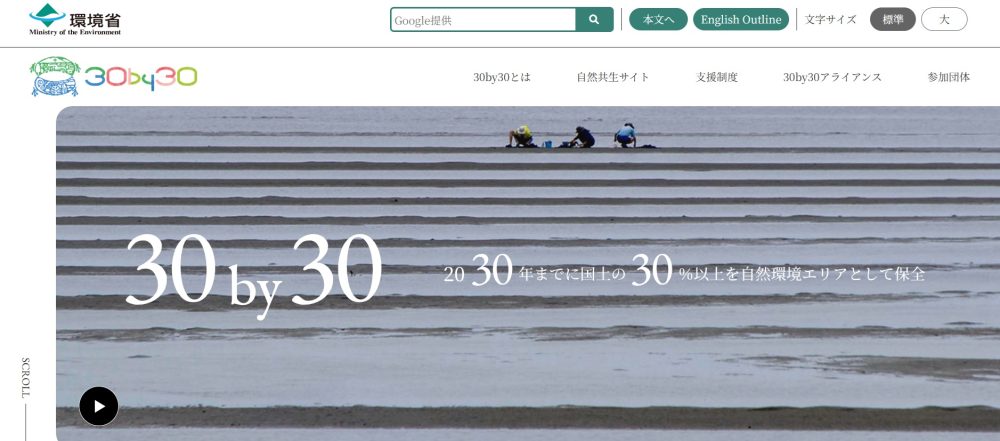
————同月、「龍谷の森」が関西私立大学で初めて、環境省の「自然共生サイト」に認定されたこともニュースになりました。
村井:「自然共生サイト」は、ネイチャーポジティブの実現、30 by 30目標(2030年までに陸と海の30%以上を保全する目標)の達成に向けて、環境省が認定を進めています。目標を達成するためには国有林や国立公園といった国の保護地域だけではなく、民間が主体となって守っている森や里山、都市の緑地などを増やしていくことが必要不可欠です。
これまでの「自然共生サイト」の取り組みを強化していく趣旨で、2025年の4月から、新たに生物多様性増進活動促進法が施行されています。それに伴い「龍谷の森」も新たな制度への移行が必要です。さらにネイチャーポジティブ宣言から1年が経過し、具体化への期待も高まっています。改めて龍谷の森の活用方策や保全・維持管理などについて検討を進め、アクションを起こしていく時期にきています。
————これまで教職員や市民が中心となり保全を進めてきた「龍谷の森」ですが、今後、どのような体制が必要だとお考えですか。
村井:1994年度、龍谷大学は、グラウンド開発など教育施設として活用することを目的に里山林を購入しました。しかし開発前の環境アセスメント調査の過程で、絶滅危惧種(当時)のオオタカの生息を確認。本当にこの自然豊かな森林を壊してグラウンドなどをつくるべきなのか、学内で幾度も議論がなされた末、2000年度、教学的利用・教育研究の場として森を活用していくことを決定しました。
そこから約25年、教職員、学生、市民の方々、見学者…森に入る人それぞれがそれぞれの観点で「龍谷の森」を活用してきたと言えます。昨今の「龍谷大学ネイチャーポジティブ宣言」の発出、「自然共生サイト」認定といった新しい流れもありますし、大学として「龍谷の森」の方向性、将来ビジョンを明確に示す時期にきているのだと思います。2024年11月には龍谷の森利活用検討ワーキンググループを発足させ、課題や今後の方向性を検討しました。今後、優先順位をつけて具体化を図っていく予定です。
課題を解決し世界が注目する「龍谷の森」へ
————ワーキンググループの議論の中で、どのような課題があがりましたか。
村井:「龍谷の森」の生物多様性を維持・保全していくためには、人の手を入れていくことが必要だということ。ありのままの形で自然を放っておけば生物の多様性が守られるかというと、そのようなことはありません。下草を刈ったり、間伐したりして、森の中に光を入れていかないと、地表に光が届かなくなり、暗い森になる。土地は痩せ、生物の種類が減り、生態系が崩れてしまいます。そのほか、今にも倒れそうな状態の木々や倒木への対応などの安全面、案内板の整備などの魅力を伝える工夫、より管理しやすくするための取り組みなど、さまざまな課題が持ちあがりました。
————「龍谷の森」をより良い方向へ推進していくために、どのようなビジョンを共有するべきでしょうか。
村井: 龍谷大学が400周年を迎えるタイミングで一定の成果をあげることをめざし、3つの観点を持つことが重要ではないかと考えています。1つ目は瀬田キャンパスのみならず全学的視点で魅力を発揮すること。瀬田キャンパスの隣にありますから、瀬田キャンパスに通う学生、教員は授業の一環、研究の一環で「龍谷の森」を使います。けれど、深草キャンパスや大宮キャンパスの学生、教職員が森と触れ合う機会はまだまだ少ないと感じます。潜在的な価値は非常にあるのに、充分に生かしきれていないのです。全学で推進していく姿勢が重要です。
2つ目は、生物多様性を守り、かつ価値創造の源泉になること。大学が土地を購入する前は、里山として地域の方がこの森に入って、薪を切ったり、山菜やキノコを取ったり、人と共存してきた森でもあります。そのような経緯を尊重し、引き続き生物多様性を守っていく必要があると考えています。また、新しい研究の実施や新しい何かを社会実装するテストフィールドとして活用していくといったことも大事な視点です。言い換えれば、今日的な保全と利活用のあり方を模索するということです。
3つ目はこれからの時代、「龍谷の森」を持っていること自体が大学の持続可能性を高め、持続可能な社会の実現を先導する象徴となりえること。森を持たない大学と比べて、森を有する龍谷大学の取り組みや歴史、実績は持続可能な社会の実現に向けて説得力があると思います。
————これからの龍谷大学に望むことは?
村井:これまでは、一部の教職員のボランタリーな努力によって「龍谷の森」が維持されてきたという側面があります。大学として、将来ビジョンに到達するための方向付けをしながら、必要な体制づくりや支援を行い、一つずつ取り組みを進めていけば、きっとより良い「龍谷の森」になっていくと思います。
また2025年2月には「龍谷大学 ネイチャーポジティブ宣言」の具現化のひとつとして、台湾農業部林業及自然保育署及新竹分署、里山賽夏の3者において、龍谷の森における友好森林関係の覚書を締結しました。双方が有する里山を森林教育の拠点とし、自然共生社会の実現をめざすこととしています。国際的な議論の中で、生物多様性の保全に対する先住民族の知見の重要性が意識され始めています。世界的にも注目に値する取り組みを生み出すチャンスでもあります。
現在、環境省と協定を結んでいる大学は龍谷大学だけです。環境分野を先導する大学、ネイチャーポジティブを先導する大学という立場で、日本国内はもとより、世界の期待に応え続けていくことが重要だと思います。






