2023年12月15日、龍谷大学はDX(デジタルトランスフォーメーション)への連携・共創を推進する目的で、ソフトバンク株式会社(以下、ソフトバンク)と包括連携協定を締結しました。この協定に基づき、2024年度、龍谷大学とソフトバンクの連携事業として「ハッカソン」が実施されました。
「ハッカソン(Hackathon)」は、プログラムの改良を意味するハック(hack)とマラソン(marathon)を組み合わせた造語で、IT技術者たちがチームを組み、与えられたテーマに対してソフトウェアやサービス、モノを開発し、アイデアの斬新さや技術の優秀さなどを競うイベントです。ソフトバンクが社内で実施している手法をもとに、龍谷大学 瀬田キャンパスで学ぶ学生が「ハッカソン」に取り組みました。
2024年度のテーマは「スマートキャンパス ハッカソン」。先端理工学部・先端理工学研究科・農学部・農学研究科・社会学部の学生を対象に募集し、32名が参加。8チームにわかれてアプリなどを開発しました。
2025年度はソフトバンクに加え大津市と手を組み、「スマートシティ ハッカソン」というテーマで実施されます。
今回は龍谷大学先端理工学部 教授で、2024年度当時に瀬田キャンパス推進室長として「ハッカソン」の設計に深く関わった松木平 淳太先生に、「ハッカソン」の意義、2024年度の経緯と成果、2025年度のテーマについてお聞きしました。
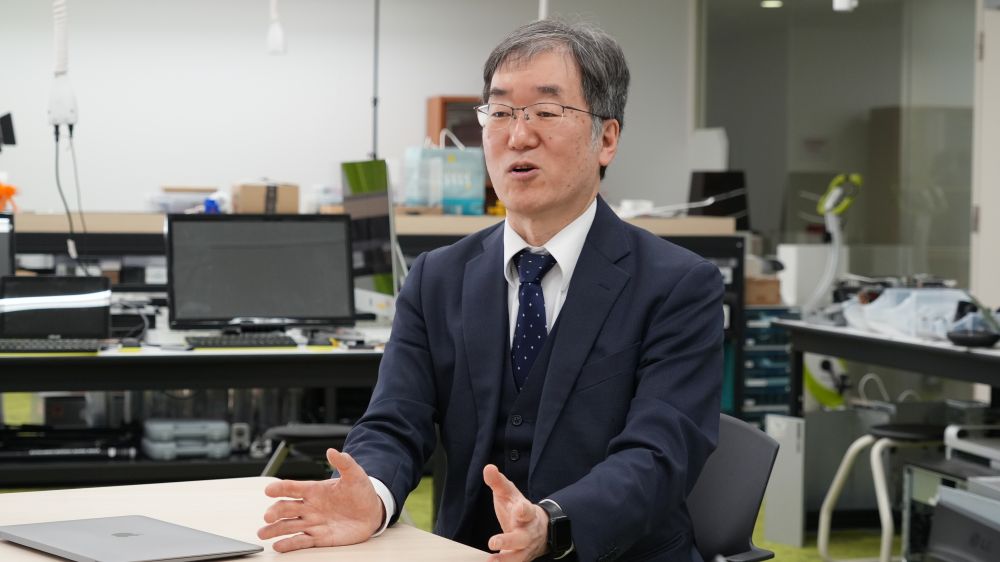
ITやデジタルを駆使し、チームでアイデアや技術を競う「ハッカソン」
――龍谷大学がソフトバンクと連携し、「ハッカソン」を実施することになったきっかけを教えてください。
「京都で開催された会合で、ソフトバンクの宮内謙 特別顧問(前・会長)が本学の前学長である入澤のスピーチを聞かれたそうです。宮内氏は、龍谷大学が仏教の教えをベースにしながらも先駆的な取り組みをおこなっていることに興味を持たれ、入澤と意気投合。その場で、『手を組めば、何かおもしろいことができるだろう』と話したことがきっかけとなり、本学の客員教授に就任いただきました。
その後龍谷大学とソフトバンクが協定を結び、宮内氏には本学学生に向けた講演会を開催してもらったり、先端理工学部教員の研究にコメントしてもらったりするなど、連携を深めてきました。また、宮内氏には2027年4月の設置を計画している「情報学部」(仮称)のスーパーバイザーに就任いただく予定であり、これまで培ってこられた経験やネットワークを活かしてもらうことを期待しています。
宮内氏だけでなく、ソフトバンクのエンジニアの方にも関わってもらい瀬田キャンパスで何かやろう、学生も教員も学びになる内容にしよう、と考えた結果、ソフトバンクの社内で若手エンジニアを中心におこなわれている「ハッカソン」を、龍谷大学でも実施することになりました。ソフトバンクが大学の学部生と一緒にハッカソンをおこなったのは初めてのことです。
ソフトバンクは若い感性を大切にしている会社です。しかし会社には同じような意識をもった社員が集まっているので、どうしても似たようなアイデアばかり集まってしまうと聞きました。ソフトバンクとしては、技術者が学生の自由な発想に刺激を受けたい、大学で研究されている最先端の技術に触れたい、技術者の育成に寄与したいという狙いがあるようです。
本学としては、学生の学びが大きく飛躍すること、社会に出たときに、チームメンバーとのセッションする経験が生きることに期待を込めました」。
――2024年度のテーマは「スマートキャンパス ハッカソン」でした。
「テーマの内容は『ITやデジタル技術の力で、瀬田キャンパスを良くしよう』です。瀬田キャンパスの学部・研究科を横断して32名の学生が参加し、1チーム4名の8チームを編成しました。チームは、個々のアイデアや専門性を発揮できるよう分野が異なる学生で構成されました。
ソフトバンクと包括連携協定を締結したのが2023年12月、ハッカソンの説明会が2024年4月下旬。実施は6月15日〜8月10日の計4回で、スピード感のあるスケジュールでおこなわれました」。
――ハッカソンの、4回の様子を教えてください。
「初回は、概要説明、チームのメンバーと初顔合わせでした。ソフトバンクのファシリテーターから『20分間で、チーム名、何をやるか、リーダーを決めてください』と指示があり、学生たちは短い時間のなかでそれらを決定していました」。

「2、3回目はLINEやAPI、Azure技術の説明とディスカッションです。学生同士がディスカッションしたり、キャンパス内のものづくり施設・STEAMコモンズでプロトタイプを作ったりと、朝から夕方遅くまでみっちりとおこなわれました。
ソフトバンクの社員がファシリテーター、サポーターとして同席されたのですが、困ったときにすぐ解決案を提示するのではなく、学生たちがやりたいことを尊重し、チームみんなで考えるように促していたことが印象的でした」。

「4回目は8月上旬です。1泊2日で、学生と教職員で東京に向かいました。初日はソフトバンク本社を見学し、最新鋭の施設を目の当たりにしたことで学生たちも大いに刺激を受けていました。そして、2日目に発表会、最終審査会、授賞式がおこなわれました」。
「ハッカソン」審査の基準は技術力、斬新さ、プレゼン力
――学生たちのアイデアはいかがでしたか。
「瀬田キャンパスをもっと便利にしたい、もっと快適に過ごせるようにしたいという熱い想いを感じました。どのチームも、それらの想いをカタチにするべく、ITやデジタル技術を活用してアプリなどを開発していました。
審査の基準は、有用性、実現可能性、斬新性、技術的チャレンジ、モノづくり活用の度合い、テクノロジー活用の度合い、そして審査会でのプレゼンテーションにおける表現力です。
1位に選ばれたのはチーム「include.R」のwebアプリ「ru Bridge」で、学生たちが所属する部活動やサークル、団体がメンバー募集やイベント参加の呼びかけができるプラットフォームです。お知らせをする際にSNSを活用している団体は多いのですが、興味がある人に情報が必ずしも届くとは限りません。しかしこのアプリがあれば、学生は学内団体からの報告を確実に得ることができます。
本学の学生全員がもつGoogleアカウントと紐付けられており、学生がこのアカウントでログインすると閲覧できる仕様になっています。そのため、龍谷大学の学生だけが安心して使えるというわけですね。さらに、アプリの認知度を高めるため、STEAMコモンズでオリジナルバッジのサンプルも作成していました。アプリ開発だけでなく、アプリが実装化された後に学生に認知してもらう工夫まで考えられているのも評価につながりました。ソフトバンクの社員さんからは『このアイデアはきっと売れる』というコメントをいただきました。
ほかのチームのアイデアでは、空きコマを有効活用して学生交流につなげるアプリ、キャンパスに通じる暗い道路に設置するスマート照明システムなど、すべてクオリティが高く、ソフトバンクの社員も私たち教員も驚きました」。
2024年度「スマートキャンパス ハッカソン」に参加した学生のインタビュー動画
2025年度のテーマは、生成AI×地域課題の解決

――2025年度新たに大津市とも連携し「スマートシティ ハッカソン」を行うそうですが、この狙いについて教えてください。
「瀬田キャンパスは1989年、大津市に開設しました。その後、全国に先駆けて地域貢献活動の拠点としてREC(Ryukoku Extension Center)を設け、地域の人々への公開講座や中小企業やベンチャー企業の技術・研究開発を支援する産学連携事業を推進してきました。また、大津市とは大小様々な取り組みにおいて連携してきた歴史があり、産官学連携の文化が醸成されています。
大津市としても、2019年にソフトバンクとスマートシティの推進における連携・協力に関する協定を締結しており、ソフトバンクと大津市とともにスマートシティをテーマにした「ハッカソン」を行うこと自然な流れと言えます。
「ハッカソン」では、大津市はオープンデータだけでなく地域課題に関する様々なデータを提供。そして審査会には審査員として参加してもらうことで、学生たちのアイデアを現場の視点で評価してもらいます。舞台をキャンパスからシティに広げることで、学生にとってはより実践的な学びを得る機会になります」。
――「スマートシティ ハッカソン」では学生にどのようなことに期待されていますか。
「キーワードは生成AI、オープンデータ、スマートインフラ、グリーンDX、農業IoT、琵琶湖、水管理システム、モニタリングなどです。大津市の地域課題を解決する、学生のアイデアに期待しています。
2025年度は、先端理工学部・農学部の2年生以上の学部生および大学院生を対象とします。技術やプレゼンの力を磨きたい、みんなでひとつのモノを作り上げたいという学生のみなさん、参加をお待ちしています」。







