=============
執筆:龍谷大学文学部 高橋(仏教学科)、瀬戸(仏教学科)、櫻井(歴史学科東洋史学専攻)、池田(歴史学科文化遺産学専攻)
※本記事は龍谷大学文学部のPBL演習内にて編成した「地域政策グループ」の学生が執筆しました。
=============
2023年、京都市は観光客数、観光客の消費額ともにコロナ禍以前の水準を超えました。観光により経済的な恩恵をうける一方で、交通機関や観光地の混雑、観光業と地域社会の共存、観光客へのマナー啓発が課題となっています。実際、京都市内に通学する私たちも、市営バスの混雑により観光客の波に飲まれた経験があります。観光混雑は、京都で学生生活を送る私たちにとっても身近にある問題です。
私たちは、観光と地域の政策や取り組みに関心をもつメンバーで「地域政策グループ」を結成。ワークショップを重ね、京都市の観光プランを数多く企画する観光事業者の取り組みに注目しました。
地域固有の体験メニューを紹介する
「LINK KYOTO」
私たちが注目したのは、JTB京都支店が運営する「LINK KYOTO」というwebサイト。「LINK KYOTO」は、京都の地域産業や事業者との関係性の向上、ステークホルダーと共に地域固有の体験メニューをつくること、持続可能な地域社会の実現に観光で貢献するという点を重視した、JTBが手掛ける観光プラットフォームサイトです。今回は、この「LINK KYOTO」立ち上げの目的や地域社会との関係について、担当者である濱村紘史さんにお話をうかがいました。

観光におけるサステナビリティ
濱村さんは、「京都市が域外からの観光客によって経済的な恩恵を受ける反面、混雑や騒音などによって地域住民が困っている現状もある。観光と住民の生活の調和がとれていない」と現状を分析。「LINK KYOTO」のサイトにおいても、京都の生活環境や伝統文化に悪影響を及ぼすような過度な商業化を避けることで本来の京都の姿を守ることを優先としたツーリズムの在り方へのシフト、を理念として挙げられています。
「LINK KYOTOが重視するのは観光のサステナビリティ。地域と観光の関係についてさまざまな課題が挙げられる中で、京都市とも相談しながら、地域と観光の間で摩擦が起きない方法を常に模索しています」と濱村さん。
「LINK KYOTO」では、京都市が運航を手掛け、バス内に大きな荷物を持ち込まないようにする為のハンズフリーバスや、早朝や夜の時間帯の観光コンテンツを掲載し、分散観光を推奨するなどして地域住民の生活に支障が出ないような観光を提案しています。
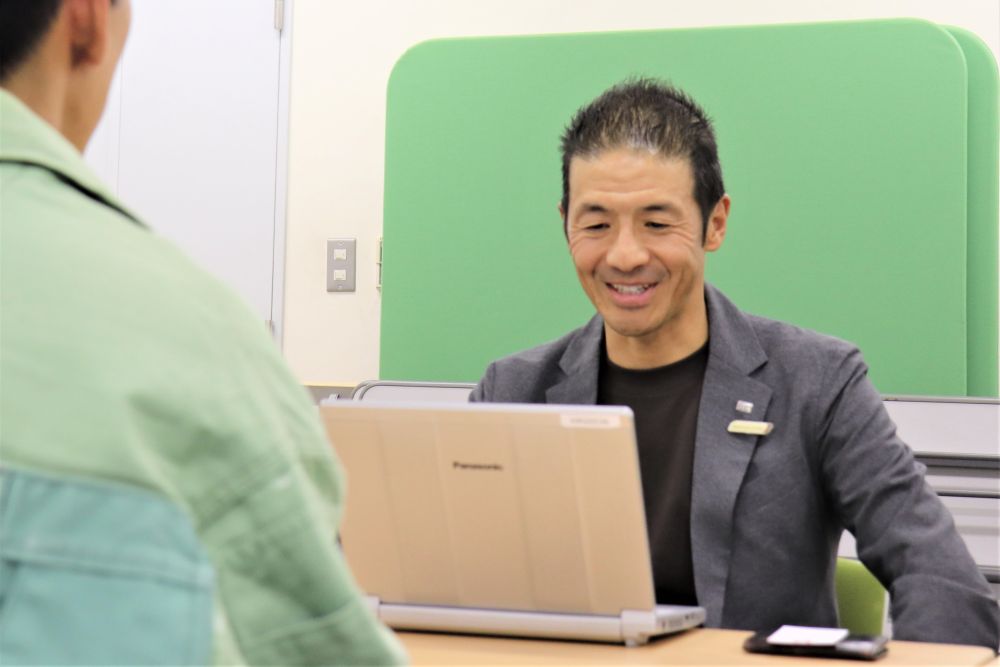
JTB・濱村紘史さん
伝統文化の紹介で「観光」を地域社会に還元
地域への還元について、具体的にできることを聞いてみました。
「修学旅行などの教育旅行によって、訪れた学生が伝統文化に興味を持ってもらうことで、ひいては担い手不足の解消など伝統文化の保存につなげたいと考えています」と、濱村さん。
「LINK KYOTO」には、舞妓さんの歴史と伝統文化とのかかわりを学び、実際に舞妓さんと対話できるプログラムや、京都伝統工芸大学校で伝統工芸の継承に関わる現場を見学し、職人さんの声を聞くことができるプログラムなど、伝統文化に関わる方々と実際に対話できる教育プログラムが多く紹介されています。
また、濱村さんは「旅行者に京都の伝統産業を知ってもらうことで、伝統産業の継承者の方たちにはその魅力を再発見してもらいたい。この再発見は、地域の『誇り』の醸成に繋げられるのではないでしょうか」ともおっしゃっていました。
旅のプロであるJTBが伝統産業と旅行者をつなげることで、伝統産業の魅力をその担い手自身にも再認識する機会が生まれます。その再認識が「誇り」の醸成に繋がり、そして観光によって生み出された新しい価値が地域の人々へと還元される、という循環を作りたいという想いを知ることができました。
「観光を通して、地域住民に貢献できることは何か、地域住民の代弁者である京都市と観光業に携わるJTBが意見交換をしながら模索し続ける必要がある」と濱村さんは言います。企業として、今後どのような方法で地域住民と連携していくのかという期待を感じました。
魅力ある町づくりの第一歩は、
地域住民が地域や文化に「誇り」を持つこと
今回の取材を通じて、観光商品を販売する側の企業が、旅行者だけでなく伝統文化の担い手や受け入れ側の地域住民を強く意識していることを知りました。また、京都の魅力を国内外に発信するためには、地域住民が旅行者を気持ちよく受け入れることが前提となることがわかりました。地域住民や伝統文化の担い手がそれぞれのまちや文化に「誇り」を持つことが、持続可能かつ発展性のある観光都市・京都の第一歩なのではないでしょうか。






